#86
平成19年5月
|

このページは、色々な方にご協力いただいて、
唐津のおみやげ話をお伝えするページです。
バックナンバーもご覧頂ければ幸いです。
#1 御挨拶
|

|
monohanako
やきものの『モノ』と英語の『単族』という意味をふくませた、
世界にただ一つしかない花子のやきもの。
|
みなさん、こんにちは。
今月は、特別企画です。二人の素晴らしい女性をご紹介します。
一人は、中里花子さん。もう一人はその友人のプレイリー スチュワート ウルフさんです。
花子さんは、16年のアメリカ滞在から軸足を日本に戻して、このたび唐津市見借の地に[monohanako]を設立しました。
父の中里隆先生からは独立した彼女固有の陶芸を展開していきます。その花子さんをよく知るプレイリーさんは、現在花子さんの窯に滞在して、深く日本の文化を体験しています。
今回は、プレイリーさんに、英語で花子さんを語っていただきました。原文のほうはこのページの英文版のGreeting
5月号に載せています。原文をお読みになりたい方は、こちらをクリックしてください。
この日本語版は大河内はるみの翻訳でお届けします。
また、monohanakoのイメージをこわさないために、今回はカラーの写真をつけません。
では、どうぞお楽しみ下さいませ。
みなさんが花子さんのファンになってくださることを願います。
|
| |
中間の場を塑る
by プレイリー スチュワート ウルフ
|
佐賀県唐津市郊外の高台に殆ど人家のない狭くくねった道路から2本の小道が並んで分かれて、すぐに互いに遠ざかる。二つの道は波型トタンの外壁の54フィートほどの長方形の建物の両側を通るのだ。4月のある夜、9時。外の春の雨の規則的な音が屋内に低く流れるバッハのセロ組曲のおだやかなメロデイーと交錯する。快適な涼しさだ。今はやさしい季節。冬の冷たい湿気と夏の過酷な蒸し暑さとの間を癒す気候。中では中里花子、34歳、陶芸家、がロクロ近くに座って板一杯の半乾きのカップに取り組んでいる。花子は5フィート3インチ、肩幅は広い。樫の木の色の肌が広い頬骨の上に広がり、薄い唇は少々しかめ気味だ。座っている席は一列の景色のよい窓に面している。窓ガラスが明るく照らされたロクロ場と外の雨夜の濃い闇とを隔てている。窓は花子の後方のいろいろの物を映し出す。この部屋はセメントの床から周囲の壁面全てが木で建ち上がっている。壁板は杉で、太い木の梁が高い屋根を支えている。この家はホンモノの材で丁寧に作られたホンモノの構造物だ。この家はシンプルに端整であり、寡黙ながらも作り手たちの匠の技を誇っている。
唐津生まれ、16歳で日本を出てその後の16年をアメリカで過ごした花子。長い一日の終わりにさしかかる。日本に戻って1年、この新しいスタジオでわずか3ヵ月半。今、花子はひどく忙しい年になりそうな一年の第二段階に入っている。日本全国で10箇所と、ニューヨークで一つの個展の予定があるため、最近の花子がスタジオを離れるのは、食べること、寝ること、そして個展打ち合わせのために出かける時だけだ。今夜花子は一塊の土を目の前のカップに付けて引き伸ばし、優雅な広い持ち手にしてカップをマグに変えていく。この人気の磁器のマグは花子の定番デザインものの一つであり、彼女が始めたビジネス、[monohanako]の'the
bread and butter' (基盤商品)である。「自分でもびっくりよ」と花子が顔を上げて言う。眉の細い弧の下の大きな茶色の目の光は強い。左の眉には銀色のピアスが光る。「仕事があんまり多くて一年前にはどんな気がしてたか忘れてしまった」 花子が言っているのは日本に帰る、そして1989年に出た故郷に陶房を築くと決心したころの不安な気持ちのことだ。
「私は今ここにいなきゃいけないんだよね。ふりかえるのはダメ。ウインブルドンでテニスやってるようなものね」
テニスを持ち出したのは、花子にとっては唐突ではない。中学生の時花子は優秀なテニス選手だったのだ。九州ジュニア杯で優勝したあと花子は2週間フロリダのニック・ボレッチエリ テニスキャンプに参加させてもらった。戻ってからは日本の「勉強オンリー」のやりかたがわずらわしくなった。その年頃なら誰しもだが、一流大学に入るという予定されたゴールに向わなければならなかった。「日本ではそんなものなのよ」 花子に言わせると日本の若者の生活は敷かれたレールを進み、予定された成果を上げるべく楽しくもない数年を送るだけなのだ。「急に意味がなく、空しく思えたの。そんなの興味ない。’普通’の生活じゃないものを経験したかった。違う文化の中で、違う考え方に出会いたかったの」
1989年に花子はテニスと学業の目標を達成させてくれる所だと信じてフロリダ高校で2年生となった。だが満足がいかず、高校を転々としたがいい教育といいテニスコーチが両立しているところはなかった。高校卒業後フロリダに戻った花子の気力は萎えていた。「私は自分の限度がわかったの。フロリダには合わなかった」 けれども家に帰ることはやる気のある10代の選択肢になかった。「家には帰れない。テニスに燃え尽きて家に帰るのは負け犬でしょ」 花子はラケットを捨ててマサチューセッツ、ノーサンプトンのスミス・カレッジに入学した。
朝7時半。朝日が裸の赤土と雑草だけの斜面を照らし出す。最近何かを建てたばかりの場所の風景だ。花子は小さな自宅から下のスタジオへ新しくつけた小道を下る。短い黒髪はファッショナブルにグシャグシャだ。春を告げたサクラはもう散り、日に日に緑が濃くなっていく。スタジオの屋根はやわらかに傾斜して廂は深く、一列の影を作り、その影は北から南へ日の歩みと共に移動し、窓を暖める。花子は部屋に入りアイポッドのスイッチを入れる。いつもの相棒だ。ゴタン・プロジェクトのアルゼンチンタンゴが部屋を満たす。仕事場を整えるのに数分、ロクロに向って座る。袖を捲り上げて、ロクロをまわし始める。6月と7月に3回の個展を控えている。2000個の器をつくらなきゃ、と計算していた。しかも、大急ぎで。ロクロは最初の一歩に過ぎない。底を削り、素焼きして釉薬をかけ、火入れ、分類して札をつけ梱包して展覧会場に送らねば。ロクロ上の土の大きな塊にかがみこみ、繰り返し強い腕で土を円錐形にもみ上げ、またそれを押し戻す。それから両手の間にこぶし大に土を掴み取り、丸める。指と手のひらの間で土を押しながらあたらしい器を作っていく。「私は形がすきなのよ」と花子は言う。「それから、動きとそれに直接かえってくる反動がすき。僅かの動きが土に響くの。感能的だと思う。焼物って、感能的よ」
器の回転につれて花子の頭がゆれる。わずか数回のすばやい動きのうちに土は繊細な器に変わる。回転しているうちに口作りをなめらかにして、底を糸切りし、下のほうのまだ形になっていない土から切り離す。「やきものは即興的なの」と花子は言う。「でも同時に長い時間掛かるとも言える。感じがちがってくるのよ。火を入れると変わるし」 出来上がった器をそっと持ち上げ、右側の板の上に乗せる。そして次に取り掛かる。花子の動きは速い。何度も何度も繰り返す。
花子のロクロの敏捷さはおびただしい訓練の量の賜物だ。そんな訓練を受けようとはしんから思っていたわけでもなかったのに。1996年にスミスカレッジを卒業してから花子は現実に直面した。学校を出たらもはやアメリカにとどまるビザがないということだ。「そんなこと、考えてなかったの」 話し続ける花子の目に後悔が宿る。「現実に突き当たったわ。人生とビザを考えるためにもう一年あった。私にはなんの腕もなかった。すしバーで働こうか、日本語通訳でもやろうか」 雇ってくれる人を数ヶ月探して、落ち込んでいた。「自分でも納得できないのに、雇い主を納得させるなんてできっこないよ。帰らなきゃしかたないと感じていた」
その頃花子の父で高名な陶芸家の隆は世界各地のアートセンターで活動していた。花子はデンマーク、コロラド、ハワイで父の助手を勤めた。父と共にあった時間は花子を土に向わせた。「でもあの時は、やきものをやろうとはっきり思ったわけではないの」 しかし父は娘に花子が今までやきものと結びつけて考えたこともなかった一つの生き方を示していたのだ。「父は旅をしてちがう人たちに遭えることを見せてくれていたの。陶芸家だけでなく、建築家、デザイナーなど。とても刺激を受けたわ」
花子は父と共に唐津に戻って子供時代暮らした家へ帰った。風の通る大きな家は緑濃い谷を見下ろしていた。けれどもこの家は将来を考えるには静かなところではなかった。自然に囲まれて牧歌的なところではあったが、隆太窯は忙しい焼物生産の場所であった。弟子達がスタジオで立ち働き父と兄がそれぞれの個展のために制作する多忙な現場だった。4人のスタッフが作業場を切り盛りし毎週何百個もの器が整理され、札をつけられ、包まれて発送された。家の広い台所では炊事人が全従業員の食事を用意している。のんびりした手はここでは許されない。スタジオのペースは花子に土と遊んでいることを許さなかった。花子はその頃を回想する。「土にさわりたければ、弟子入りするしかなかったの」 ほかに計画がなかったこともあって、花子は弟子入りをした。2年半の間花子は自宅に住んで父の弟子となった。隆太窯で一日中掃除をして、土もみをし、薪割り、釉薬掛け、窯焚きをした。早朝と夜半にロクロの修行をし、寸分たがわず同じものが出来るまで一つの型をひき続けた。
花子の夢はやはりアメリカに戻ることであった。「アメリカに帰りたかった。日本は私のいる場所でないような気がしてたの」 アメリカでは自分の家族や文化の文脈を離れて自己を表現することが出来ることを経験してきた。そして離れていた時間は花子に日本を遠くから見る機会を与えた。「日本の外で自分のアイデンティティを創るということは自分の文化的なアイデンティティである日本文化をよく見ることになったし、それは大切に思えた」 アメリカにいる間に花子は日本の宗教と、茶の湯をふくむ日本文化の核芯を学んだ。花子は日本文化で深く敬意を払えるところと、ひとを共通の型にはめようとし、そのために彼女が離れたくなった部分とを切り離して見ることが出来た。彼女は選択的に見れるようになったのだ。 「私は日本の好きな部分を選び取り、自分のその部分だけを強調することができるようになったの」 しかし離れていた時間は花子が日本の社会に円滑に再び入るには妨げとなった。「私はかえって日本的になって戻ってきたのに、人は私をアメリカナイズされた女の子としか見なかったの。私は自分の町で、よそものだと感じていた」 花子は再び日本を出たいと切望するようになる。 「でも、何の腕もなくて家をでるわけには行かなかった。今やってることが気に入ってなくても、一応はやり通そうと思ったわ」
修行が終わり、陶工としての腕を身に付けてから花子はアメリカに戻る道を探した。 国際的に知られた陶芸家である花子の祖父のもとで1960年代に学んだことのあるアメリカ人陶芸家マルコム・ライトが、彼の工房で陶工として花子を受け入れることを承知した。花子はやきものを「テニスと同じ。アメリカに帰るドアよ」と言う。「でも、やきものを一生やります、と決めるつもりはなかったの。今は陶工だけど、他のことやるかもしれないしね」 2000年に花子は再び日本を出て、ニューイングランドに住み着いた。書類上では花子はマルコムの窯の雇い人だったが、実際には自分のやりたいことが自由にやれた。 「隆太窯を出るとかえって焼物が楽しくなったの。自分の形を作るのが楽しかったし、驚いたことにそれがよく売れたの」 花子は続くだけやってみようと言う口実で、やきものを続けた。マルコムのスタジオでは5年間仕事をした。「私の作品はどんどん売れたのよ」 花子はこともなげに言う。「ほかの道もある、って思うのをやめたの。やきものを受け入れ始めていた。そして、この道に決めたの」
花子の作品はアメリカでも売れたが、大部分は日本で売れた。親子展で出し、それが個展になり、花子は器をアメリカで作り80パーセントを日本に送るということになった。陶芸は花子にアメリカに住む機会を与えたが、性格的に合うアメリカは職業的には不十分であることがわかってきた。2002年に花子の父はガンの診断を受け、その3年前に母も病を得ていた。両親はともに病気を克服したが、花子の心は家族に引き戻された。加齢という現実に直面した両親は身辺を整理し始めた。隆太窯は花子の兄に譲るという方針が取られ、家業は息子に引き継がれた。隆太窯を離れたところに両親の家が新築され、そこで両親はこれからの日々をすごすことになった。そして花子の作品が売れるにつれて、マルコムの窯の枠から花子ははみ出していった。
花子は昼食後広いダイニングテーブルに向って通信などの仕事を片付ける。近まる個展の作品の発送のことで展示会場と話をつけなければならない。先方は早い入荷を望むが、こちらは制作に時間が欲しい。目の前には2枚の大きなガラス戸から右下にスタジオの屋根を、ほんの数ヤード左下に両親の家を見下ろせる。その屋根越しにたたなずく山並みを遠望する。 「自分の生き方がこんなふうになるって、考えたこともなかった」花子は意外の口調で言う。「これが見つかってほんとによかった。これがほんとの私よ」 自分でも驚く言葉が口から出る。「1年前はすごくナーバスになってた。私は、これはほんとは望みとちがうと思いながら唐津にスタジオと家を作ろうとしてたの」
花子は窓の外に目をやる。成形前の粘土であふれた広いスタジオ、手を入れて庭にしなければいけない山肌。そして手の届くところにある両親の家。 「これは重大な挑戦よ」 花子の声には疲労と決意が重なり合う。「私は私であり、うちの家族から自立しているってことを世間に示さなくちゃ」 家族、中里家。父、祖父、その前の12代にわたる陶工の血。それは日本の陶芸会においてゆるぎない地位を誇る血脈であり、花子の最善の財産でもあり、最悪の重荷でもある。中里家であることはすなわちそれだけで評価される。花子は自分自身を評価されることを願い中里家とみられることを拒んでもがく。もちろん唐津焼から、そして父の焼物から多くの影響を受けているとはいえ花子の作品は驚くほど異なる。「伝統って、そこから学ぶべきものであり、まねするものではないと思う」花子は言う。「唐津焼はモダンではない。私は唐津焼の骨格は好きよ。気骨があるもの。私の焼物は骨格は唐津。でも肉と皮はモダニズムや形、そして機能美が面白い。スカンデイナビアのデザインに惹かれるの」
花子が自作を評していう唐津の骨格に西洋の装いとはまさに言いえて妙な表現である。花子は二つのアイデンテイテイ、すなわち芯が日本で外側が非日本的な性格、に折り合いをつけた。花子は再び日本に戻って、最初に隆太窯の弟子として日本社会に入ったときと同じ難しさに直面している。花子の出自により、また、家から離れていた歳月により、人はいろいろの憶測を持って花子に会い、その先入観は花子に重くのしかかる。けれども今度は花子は言う。「もう大丈夫よ。よそ者の気がしても。よそ者のほうが時にはちがった角度から物事がはっきり見えることもある。違う目を持てるって、ありがたい。その気持ちが私を後押ししてくれる。インスピレーションになるわ。私は私独自のやりかたで文化の梯になりたいもの」
花子はそのとおりのことをやっている。土で、強くかつ優しい形を作り上げ、その形は誇り高く既存の色分けを拒む。それらは明らかに日本の器なのに、明らかに単なる日本の器ではない。花子の応援者たちの幅が広いのは予測に難くない。6月には東京の万葉洞で個展がある。万葉洞は茶道に通じた定評のあるギャラリーである。7月にはニューヨク市の新しい革新的なアーテイストを扱うチェルシー系のビスポークギャラリーで展示する。両方の展示会に花子は同じようなメッセージを送る。「全てのものは食物を軸に回転する。いかに食べるかが私たちが誰であるかを決める。日本の食文化はユニークだ。日本人は卓上に色々な皿を取り合わせる。ところがアメリカでは全部の皿がユニフォームのようにそろっている。アメリカ社会は違いを尊ぶが、卓上でだけはそうではないらしい」 花子は日本でも器の用途にきまりがあるのを知っている。「お茶の文化を深く尊敬するけれど、だからと言ってお茶を安全地帯にして一歩もでないのは安易過ぎると思う。茶道はかつてアバンギャルドであり、亭主が客をもてなす場を作り上げて共にたのしむ共感の率直な表現であったはず。ところが今のお茶は作法、作法。決まりきって余裕がなくなっている。私が言いたいのは、”なんでもあり。でも何をしているのか自分でちゃんとわかって、やろう。楽しい、面白いものにしよう”ということ。私はきまりから考え方を解き放すことを知らせたい。私は伝統文化を私のやりかたで、私の解釈で表現したい」
スタジオに戻ろう。花子は乾いた器を窯の棚に積み始める。このあと12回ほど焼かなければならない火入れの一回目である。今のところは花子はガス窯を使っていて、透明と黒の釉薬を好む。花子の器は窯からモノクロームの均一な色合いで上がってくる。釉薬を掛けられ焼かれると花子の器つくりの段階は終わる。「作業は終わる、でも器はまだ完成じゃない」と花子はいう。「私が思い通りにできないところが面白いの。他人の手にわたってそこで日常の生活の中で変わっていくの。私は私の器が誰かの暮らしのなかで生きていくのを願ってるのよ」
仕事中に花子はお気に入りのアメリカのラジオ番組、NPRのフレッシュエアーをアイポッドにダウンロードして聞く。花子はしゃべるときはスタジオを見回す。ものの置き方、イスは散らばり、バケツや釉薬が積み上げられその場所はまだ人が住みこなしてはいないようにも見える。品物はばらまかれまだ落ち着きどころを見つけられずにいるように見える。でも、それ以外にどうすればいいのだ? 生まれて初めて花子は自分の場所にいるのだ。そして自分自身に追いつこうと走っているのだ。 「人は、じゃあ日本に落ち着くのねと聞くけど、ハイでもあり、イイエでもあるわ。私の頭のどこかにいつもアメリカがある。私は中間に生きたい。私の居場所はそこ。中間と言うことはどっちつかずということではない。黒を知り、白を知ることはグレイが見えてくること。そこに私はいたい」
|
|
Prairie Stuart-Wolff (プレイリー スチュアート ウルフ)
米国ヴァーモント州に生まれる。アメリカで草の根運動をした世代の両親を持つ。スタンフォード大学卒業。オックスフォード大学やアイルランドでの短期留学も経験。大学卒業後、一年間スペイン語留学の為にグァテマラへ。そこで自分の育った環境とかけ離れた文化を学ぶ。SALT Institute にてドキュメンタリー文学の勉強や、Maine Photographic Workshopで写真の勉強をするなど、彼女の文化に対する意識は幅広い。思慮深い洞察力と詩的な表現でさまざまな人類社会を描く。アメリカで母子生活を営むメキシコ人の女性を描いた『Todo Canbia』が、2005年Yankee
Magazineノンフィクション文学最優秀賞に選ばれる。現在唐津に在住。写真家としての活動もしている。 (ホームページ)
|
|
今月もこのページにお越しくださって
ありがとうございました。
また来月もお待ちしています。 |
洋々閣 女将
大河内はるみ
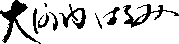
メール
|
|



