皆さん、こんにちは。僕は材木町一番組に属しています。
材木町一番組は、町内に住む若者、及び材木町に縁のある若者たちで構成されており、くんちのみならず、年間を通して町のため曳山(ヤマ)のために活動しています。まあ、もっとも亀と浦島太郎の身近で活動しているのが僕たちというわけです。今回は、くんちで見るだけでは分からない、材木町・亀と浦島太郎をもっと楽しく見るポイントについて少しだけお話しましょう。
1.動 と 静
躍動的な亀と温和な浦島太郎との対比を味わう
亀の表情をよくご覧ください。一見怒っているように見えると思います。でもどうして怒っているんでしょう。変ですね。浦島さんは亀を助けてくれたんだから怒る理由なんてない筈です。それとも、荒海を必死で泳いでいる表情なのでしょうか。浦島さんののんきな表情を見ているとそうは思えないし、第一、竜宮城からの帰りがそんな荒れ模様だなんてなんか似つかわしくないですよね。
 |
| 笑っている亀の上で澄ましている太郎さん |
僕は以前、亀の笑っている表情は怒っているように見える、とある本で読んだことがあります。なるほど、と思いました。亀は笑っているんですよ、口と目をめいっぱい大きく開けて。大好きな浦島さんを乗せているもんだから、うれしくって、楽しくってはしゃいじゃっているんですね。
さらに、亀の姿。徹底して左右非対称につくられています。尻尾の形、甲羅の形。よく見てみると、すこーし右(頭の方向)斜めに体が向いているんですね。後からみると、後足も左右で異なる動きをしていることが分かります。亀が全身を使って波を掻き分け掻き分け泳いでいる様子が巧みに表現されています。とっても躍動的なんですね。
それに対して太郎さんです。体をめいっぱい使って喜びを表現している亀に対して温和な表情で微笑んでいるだけです。上品な微笑みだと思うんです。亀の甲羅にちょこんと静かに笑って座っている。
動の亀と静の浦島太郎。そして、こんなにも対照的なふたり(?)の視線の向きは同じなんですね。
2.プ ラ イ ド
材木町の材木町としての誇りを感じとる
曳き山は台車の上に固定されているのですが、この台車は我が町の自慢なんです。
この台車は樫の木で作られています。樫の木でつくっているのは材木町だけなんですよ。
町の名前でも判るかと思いますが、一昔前までは材木屋が多くあったんですよ。材木のことなら何でも知ってるスペシャリストがいたんですね。
 |
| 自慢の樫の木の台車 |
台車を作る際には、あく抜きのため5年から7年位かけて、川につけ岸に揚げ乾燥させることを繰り返し行うんだそうです。こうすることで樫の木の本来の特徴である、堅くて粘りがあり強度が強い性質を十二分に引き出せるんです。しかし一方で、堅くて粘りが強いため加工が非常に難しいんです。それでも当時の材木町の人々は、台車にもっとも大事な頑丈さを持たせるために、樫の木でつくることにこだわったのでしょう。台車の材質ひとつにも当時の材木町の人たちの、材木町としての誇りが感じられるではありませんか。現在のものは昭和33年に作り替えられたんだそうですが、その際、その事前のものとそっくり同じものに作り替えたんだそうですよ。ですから、現在の台車も170年前の台車と変わらないわけです。昭和33年当時の先輩方も、台車をとおして天保の先人たちの思いを感じ取られたからでしょうね。
3.演 出
ゆったりとした囃子のリズムで亀の泳ぎを演出する
曳山を曳くときに欠かせないものに囃子があります。囃子ひとつで曳山の曳き方も変わり、また、曳き子の気分の盛り上がり方も変わるという、まさに、曳山を演出しているもののひとつが囃子なのです。
この囃子は14ヵ町でそれぞれ特徴があって異なっているのですが、材木町の囃子は、他町よりもテンポがゆったりとしています。遅くのんびりしているのとは違います。材木町の曳山は、比較的重くつくられています。特に、重心が曳山の後の方にあるため、曳く時も曲がる(梶をきる)時も力が必要になります。力が入りやすいテンポというわけです。なにしろ亀ですからね。重量感のある亀が、ずんずんと進んで行くテンポなわけです。
遠くから亀がずんずんと近づいてくる姿は迫力ありますよ。特に、西の浜への曳き込みは圧巻です。亀には砂浜がよく似合いますからね。そこに、心地よいテンポの囃子がさらに亀らしさを演出するわけです。
 |
| 亀の下には囃子方の子供たちが乗っている |
材木町の囃子は、主に中高生が担当しています。年間を通して月に一度、10月に入るとほぼ毎日、囃子の練習にいそしんでいます。
囃子が曳山の曳き方、曳き子の盛り上がりを演出するので、囃子方には高いレベルが求められます。特に、太鼓は囃子のテンポを決定する大事なものですから、毎年、厳正な審査のもとに担当を決めています。とはいっても、学生ですから子供たちの入れ替わりが激しく、上手な者がいてもあっという間に1~2年で卒業していきます。毎年メンバーが大きく変わって行くのです。しかし、上達が早いのも子供たち。上手な先輩が卒業してもあっという間にうまくなって、毎年すばらしい囃子を披露してくれます。
囃子方の子供たちも、必死に材木町の伝統を受け継いでくれているのです。
4.伝 統
現代の姿に天保の面影を見出す
天保12年(1841年)に制作・奉納された「亀と浦島太郎」は今年(平成23年)で170周年を迎えます。
豪華絢爛な曳山は、唐津の商人たちの豊かな財力によって競うようにつくられたと思われがちですが、僕はそうは思いません。
天保年間といいますと、天保の大飢饉が有名ですよね。東北を中心に飢饉が広がり、それは全国に波及していきます。「天下の台所」と呼ばれた大坂でさえ餓えた人々であふれていたといいます。そんな状況に何の手も打たなかった幕府に逆らって大塩平八郎が乱を起こしたのが、天保8年(1837年)なんです。唐津もこの全国的な不況に巻き込まれなかったはずはないと思うのです。2番山の「青獅子」ができてから3番山の「亀と浦島太郎」ができるまでに17年も間があいているのですが、その理由はこういったところにもあるんじゃないかと思うんです。
不況な中でも、いや、逆に不況な世の中だからこそぱっと大きなことをしたかったんじゃないでしょうか。先が見えない世の中、いつどうなってしまうかわからないという無常観。だからこそ派手な曳山をつくって曳き回し、せめてくんちの日だけでもこの世を大いに楽しみたい。この世に生きてるって実感したい。
そして曳山の制作というひとつの目標に向かって町内が一丸となる。皆で作って神社に奉納すれば、神様の御利益が得られるかもしれないと思うからです。
商人は資金や資材を提供し、職人が腕を振るう。経験豊かな年寄りは若者に知恵を伝えます。女性たちは握り飯をつくって振る舞い、子供たちは周りで遊びながらそんな大人たちを見て育つ。ひとりひとりが自分のできることを持ち寄って曳山をつくっていたんでしょうね。
僕がこう考えるのも、現代に生きる僕たちがまさにそんな感じだからです。一番組にはさまざまな職業の者がいます。さまざまな職業、能力を皆でもちよって協力しながら曳山のため、町のために活動しています。そして、女性たちはそんな男たちを陰から支えてくれる。
 |
| 子どもたちは大人の背中を見て育つ |
それぞれがそれぞれの出来ること、得意なことを持ち寄り、皆で協力しながらくんちに関わっているのです。きっと170年前もこんな感じだったんだろうなあなんて思うわけです。
曳山は人生だ、といった人がいます。
幼いころは曳山の台に乗ります。小学校に上がると綱の先頭付近につきます。そうやって曳山のコース・雰囲気を味わう。中高生になると囃子方として曳山を盛り上げます。次の曳山を背負うものとして曳山に深く関わっていくのです。
そして、社会人になると一番組に入ります。曳山の中核として曳山を運営していくのです。
その一番組を、一番組を卒業した二番組の人たちが支えます。曳山の梶棒として、また、一番組の相談役として知恵を授けてくれるのです。このシステムは江戸時代から変わっていないのです。材木町に住んでいる人は変わっても、そうやって伝統は続いていくんですね。
このような拙文・駄文を最後まで読んでくださってありがとう。ここに書かれたものは、あくまで僕の主観によるものです。人によっては違う意見もあるでしょうが、これを読んでみなさんの曳山の見方が少しでも変われば幸いに思います。
伝統は、たまたま続いてきたのではありません。それを残そうとする人々の営みの積み重ねによって続いてきたのです。それでも、さまざまな現実から続けられなくなった地域も沢山ありますが。
その地域に住むさまざまな人々、それぞれがお互いに助け合い補い合う中で関わり合い、社会が続いていく。それはどこの地域でも変わらないと思うのです。唐津には、材木町にはその中心に曳山があるのです。
曳山は、そういう地域社会の成り立ちを教えてくれるのです。
|
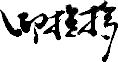 2011年11月
2011年11月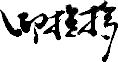 2011年11月
2011年11月